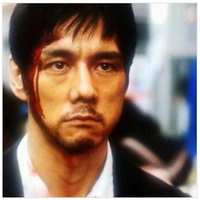2015年03月09日
静岡新聞に本田淑美さん。
3月4日付静岡新聞夕刊アットエス「こちら女性編集室」より引用。(従来は新聞からスキャンですが、事情によりネット記事をコピペしています。)
味覚で広げる復興支援
(Facebookで取り上げている方のほとんどが、折り目より上半分しか掲載していないんですよね。)
岩手の水産品を県内食卓へ 料理で復興支援 本田さん
静岡の水産加工品を、県内各地で開かれる食や物販のイベント「マルシェ」でPRする活動を始めた。被災地と交流のある同市清水区由比の桜エビ漁師の要望がきっかけ。単に商品を販売するだけではなくレシピや食べ方も併せて紹介しながら商品価値を発信し、復興支援につなげる考えだ。
静岡市葵区の女性料理研究家が、東日本大震災で被災した東北地方の水産加工品を、県内各地で開かれる食や物販のイベント「マルシェ」でPRする活動を始めた。被災地と交流のある同市清水区由比の桜エビ漁師の要望がきっかけ。単に商品を販売するだけではなくレシピや食べ方も併せて紹介しながら商品価値を発信し、復興支援につなげる考えだ。
◇マルシェにアレンジ料理
活動を始めたのは、料理教室「キッチンスタジオモグ」(葵区)代表で、テレビの料理コーナーも担当する本田淑美さん(46)。由比漁協企画の料理教室に講師として参加した縁で、桜エビ漁師の原正英さん(51)=清水区=から「被災地の水産品を使ってほしい」と依頼を受けた。1年ほど前から教室や番組紹介のメニューに取り入れてきたが、「もっと多くの人に直接、被災地の水産品を紹介したい」と、マルシェへの参加を思い立った。
主に扱うのは、岩手県大船渡市三陸町越喜来(おきらい)地区の水産加工場「漁師のおつまみ研究所(おつ研)」の商品。同地区は2011年8月に由比漁協を通じて1隻の遊漁船が無償提供されたのを機に漁師同士の交流を進めている。
原さんを介して、復興支援に参加してきた本田さんは、現地の漁師の妻らがレシピ考案から製造まで担う「おつ研」の理念に共感した。仕入れた商品に料理研究家ならではの一工夫を加えて紹介するほか、他地域の食材も取り扱う。
初出店は2月22日に清水区で開かれた「草薙マルシェ」。デミグラスソースで味付けした三陸産サンマのハンバーグや、トッピングに桜エビを添えたつみれ汁が、若い女性や主婦らに好評だった。手応えをつかんだ本田さんは「地道に出店して販路拡大につなげたい」と意気込む。
被災地との橋渡し役を務めた原さん。「漁業への震災の影響は人ごとではなく、交流から学ぶことが多い」とし、「水産品の付加価値を高めるための取り組みにつなげたい」と話す。(石井祐子)
2015年01月25日
静岡新聞に神南さん。
Facebookをやっている方はすでに目にしたかもしれませんが、静岡新聞を購読していない方もいると思いますので、掲載しておきます。
24日付の静岡新聞に、イーラブログを運営しているブレインチャイルドのスタッフの一人、神南臣之輔さんが載っています。
 「何処かで見た顔が❗️今日の静岡新聞の朝刊の25ページに出ていてビックリ。
「何処かで見た顔が❗️今日の静岡新聞の朝刊の25ページに出ていてビックリ。
当社が作成したコミュニティビジネス事例集について、掲載されました。
作成を仕切ってきた神南君、スタッフの高野さん、坂部さんお疲れ様でした。
いろいろな思いがあってそれをビジネスとして実現したい方、それを漠然と考えている方、必読ですよ。(白井昭義社長談)
24日付の静岡新聞に、イーラブログを運営しているブレインチャイルドのスタッフの一人、神南臣之輔さんが載っています。
地域課題解決へビジネス手法
県が事例集改訂
県はこのほど、地域課題をビジネスの手法で解決するコミュニティービジネスの事例を集めた冊子「県コミュニティビジネス事例集2014」(A4判、60ページ)を発行した。県内でコミュニティービジネスを展開する24の会社や団体などを取り上げた。
県が2013〜14年度に行なった「コミュニティビジネス起業支援・起業者育成プログラム普及事業」の一環。12年に作った事例集を改訂した内容で、掲載団体などにあらためて聞き取り調査し、19の会社や団体などの現状や課題、今後の目標を掲載した。
同普及事業で専門家が巡回指導した五つの会社や団体なども新たに加えた。地域の集会所を活用し、住民が交流できる憩いの場となっている「ひだまり亭」(沼津市)、子供たちに自転車の乗り方を教える「自転車初乗り指導協会」(浜松市)などで、専門家の助言内容や事業継続のポイントを紹介している。
冊子は、県の委託を受けた経営コンサルタント会社「ブレインチャイルド」(本社三島市)が編集した。1千部製作し、関係機関に配布した。希望者は県商工振興課〈電054(221)2990〉で入手できる。
 「何処かで見た顔が❗️今日の静岡新聞の朝刊の25ページに出ていてビックリ。
「何処かで見た顔が❗️今日の静岡新聞の朝刊の25ページに出ていてビックリ。当社が作成したコミュニティビジネス事例集について、掲載されました。
作成を仕切ってきた神南君、スタッフの高野さん、坂部さんお疲れ様でした。
いろいろな思いがあってそれをビジネスとして実現したい方、それを漠然と考えている方、必読ですよ。(白井昭義社長談)
2015年01月22日
いっそ・・・。
今の私にとっても大変深刻な話です。ただでさえキツい仕事だと思うのに、なぜ報酬を下げて辞める人が続出するような仕打ちをするのでしょうか。
»介護現場「賃金に不満」7割 労組調査、待遇改善が課題
»介護報酬の引き下げ決定、現場からは不安の声
»「低賃金→人手不足→過重労働」という悪循環・・・「介護労働」の現場はなぜ辛いのか
»介護職離れ、負の連鎖 低待遇・負担敬遠で職員減り…
いっそ、病人と高齢者は余命に関係なく安楽死(尊厳死)を選ぶ権利がある制度にでもしてくれたらいい。


»介護現場「賃金に不満」7割 労組調査、待遇改善が課題
»介護報酬の引き下げ決定、現場からは不安の声
»「低賃金→人手不足→過重労働」という悪循環・・・「介護労働」の現場はなぜ辛いのか
»介護職離れ、負の連鎖 低待遇・負担敬遠で職員減り…
いっそ、病人と高齢者は余命に関係なく安楽死(尊厳死)を選ぶ権利がある制度にでもしてくれたらいい。


2015年01月20日
懐かしい顔ぶれ。(前)
Tomoさん、パンタス.小澤さん、いぬのさんぽ♪さん、ONKOさん、ブログ村でよくお会いしていましたが、あれから早2年が経つのですね。あとは知らない方もいらっしゃるようです。



(写真は参加された方の記事からお借りしています。)
本日18:15より静岡だいいちテレビ「○ごとワイド news every.しずおか」で放映されます。見逃さないように録画、録画!
続きはテレビ放映後に。
»「懐かしい顔ぶれ。(後)」へ。



(写真は参加された方の記事からお借りしています。)
本日18:15より静岡だいいちテレビ「○ごとワイド news every.しずおか」で放映されます。見逃さないように録画、録画!
着物の魅力体感 「きらく場」25日オープン 三島
アットエス こち女
着物姿で多彩な体験や人との出会いを楽しめる空間を目指した「きらく場」が25日、三島市大場の呉服・洋品店「よしだ」の一角にオープンする。企画したのは、同店の吉田智美さん(47)。「堅苦しいと思われがちな着物に親しめる場所と機会を提供したい」と意気込んでいる。
店長の昌敏さんと結婚するまでは電機メーカーのエンジニアで、着物とはほとんど縁がなかった吉田さん。成人式もスーツで出席したほどだったが、呉服の仕事に携わることになり、必要に迫られて着付けを学んだ。
着物の息苦しさは着付けに慣れるうちに消え、好んで着るようになった。着心地の良さを実感するうちに、若い女性たちの「親から譲り受けた着物をたんすに眠らせたまま」「節目の日でも面倒で着ない」といった声に寂しさを感じるようになったという。
「何とか着物の魅力を伝えたい」。方策を求めて昨秋、多彩な年代や職業の人が課題解決について議論する県立大経営情報学部の国保祥子助教研究室主宰の「フューチャーセンター」を訪れた。「着物は1人だと気恥ずかしい」「仲間と一緒に着たい」−。参加した女子大学生の意見に、「きらく場」のアイデアがひらめいた。
三島市の女性起業家支援オフィス「コトリスラボ」のサポートで助成制度も学び、12平方メートルのスペース開設にこぎ着けた。名称には「気楽」「楽ちんに着る」「来て楽しむ」などの思いを込めた。
着物を着た人を対象に毎月、帯留めや手巻きずし作りなどの専門家を招いた講座を開く。15日にはプレイベントとして参加者を募り、着物で「大社の杜みしま」に出掛け、ランチを味わった。正式オープンの25日には風呂敷結びの基本講座を開く。吉田さんは「参加者と着物を来て東京五輪を見に行くのが夢」と話している。
続きはテレビ放映後に。
»「懐かしい顔ぶれ。(後)」へ。
2015年01月07日
がん患者の就活(下)。
「がん患者の就活(中)。」より続き。
8年ほど前からホームページ作成上のネッ友であり良きライバルでもあったCさん。
私のすい臓癌より1年遅れで彼も直腸癌を患ってしまい「こんなことまで競わなくても」と当時は苦笑いしました。
彼は手術で人工肛門になり、ストーマを装着していましたが、結局再発して仙骨を削る大手術を受けたようです。
その前後かなり長い就活に明け暮れて、ようやく再就職出来たらしいのですが、現在は完全に音信不通になってしまいました。私たちが使用していた無料ホームページ作成スペースからブログやコメント欄などのツールのほとんどが廃止になってしまったためです。
彼は最後までHTMLとスタイルシートを使ったホームページ作成にこだわっていましたが、私はちょうどイーラブログに鞍替えして疎遠になっていきました。彼は私のようにFacebookなどで正体を明かしている訳ではないため、こちらからは連絡の取りようがありません。今はどうしているのでしょう。
最後の頃の情報によると、幸いなことに彼が新しく採用になった会社は癌患者に理解がある(社員として受け入れる余裕がある)ようでした。再手術で入院になった時にまだ試用期間中だったにもかかわらず休暇扱いにしてくれ、復帰後も変わらず働くことが出来たようです。今も元気に働くことが出来ていれば良いのですが。
«「がん患者の就活(上)。」へ戻る。
«「がん患者の就活(中)。」へ戻る。
8年ほど前からホームページ作成上のネッ友であり良きライバルでもあったCさん。
私のすい臓癌より1年遅れで彼も直腸癌を患ってしまい「こんなことまで競わなくても」と当時は苦笑いしました。
彼は手術で人工肛門になり、ストーマを装着していましたが、結局再発して仙骨を削る大手術を受けたようです。
その前後かなり長い就活に明け暮れて、ようやく再就職出来たらしいのですが、現在は完全に音信不通になってしまいました。私たちが使用していた無料ホームページ作成スペースからブログやコメント欄などのツールのほとんどが廃止になってしまったためです。
彼は最後までHTMLとスタイルシートを使ったホームページ作成にこだわっていましたが、私はちょうどイーラブログに鞍替えして疎遠になっていきました。彼は私のようにFacebookなどで正体を明かしている訳ではないため、こちらからは連絡の取りようがありません。今はどうしているのでしょう。
最後の頃の情報によると、幸いなことに彼が新しく採用になった会社は癌患者に理解がある(社員として受け入れる余裕がある)ようでした。再手術で入院になった時にまだ試用期間中だったにもかかわらず休暇扱いにしてくれ、復帰後も変わらず働くことが出来たようです。今も元気に働くことが出来ていれば良いのですが。
がん患者の就活(下)企業側の理解不可欠ーカナロコー
県庁にほど近い横浜市中区のハローワーク横浜。相談窓口が仕切りを隔てて並ぶフロアの一角に専用窓口が設けられている。デスクには「長期療養者職業相談窓口」と記された手作り表札が。「あまり目立つと利用者が気にするから」。スタッフの小沢美弘さん(68)が配慮を口にした。
小沢さんは2級キャリア・コンサルティング技能士の国家資格を持つ就職支援ナビゲーター。2013年5月に設けられたがん患者向けの相談窓口を担当する。
仕事と治療の両立ができる社会づくりを目指す国のモデル事業で、患者の体調や治療スケジュール、希望する仕事などについて聞き、要望に沿った職場を紹介するのが役目だ。横浜市立市民病院(同市保土ケ谷区)と県立がんセンター(同市旭区)に1カ月に2度足を運び、看護師の立ち会いで出張相談にも取り組む。
なるべく残業や営業ノルマなどがなく、ストレスが少ない職種や自宅から近い職場を紹介するようにしている。利用者には回復傾向の患者もいれば、末期の患者もいて、状況はさまざま。志望に沿わない場合もあるが、「丁寧に話し合い、納得する道を探している」。スタッフがその場限りで担当する通常の窓口とは違い、小沢さんが継続して担当するため、利用者の理解を深めることで適切なアドバイスができるという。
続く模索
昨年9月末までに52人が窓口を訪れ、支援を望む利用者33人をサポートした。半数近い14人が医療機関の受付事務や飲食店の調理業務、カフェのホール担当といった仕事に就いた。
それでも「担当者としては物足りない。目標は就職率100パーセント」と話す小沢さんは「この事業を把握している企業は少ない。がん患者も働けるということを知ってもらうため、地道に取り組んでいきたい」とさらに前を向く。
一方、ハローワーク横浜の上席指導官、土屋秀樹さん(42)はがん患者の就労支援の難しさを吐露する。「正直、どの会社ががん患者を積極的に採用しているのか分からない。そもそもそういう会社があるのかどうかも分からない」
がん患者の採用や支援制度をうたう会社を把握するのは簡単ではない。県内の各企業に支援事業を説明するチラシを配布し、ホームページでも知らせているが、これまで問い合わせはなく、各企業の理解度はつかめていないのが実情だ。土屋さんは「患者が働ける環境を整えている会社があれば情報として蓄積し、間口を広げたい。どうすれば効果的に周知できるのか」と頭を悩ませている。
患者への対応も模索が続く。「できれば看護師と就労支援の両方の資格を持つ人が適任だが、該当する人は少ない」と小沢さん。自身はがんについて専門的な知識はないといい、「利用者に『医療の知識はあるのか』と尋ねられ、返答に困ってしまうことがあった」と苦笑する。
土屋さんは「まだ実績があまりないので半信半疑の利用者もいる。だからこそ関係づくりが重要になる」と受け止める。「患者のこと、病気のことを理解することを心掛けている」と話す小沢さんも、横浜市立市民病院の看護師らと勉強会を行い、バッグに忍ばせている参考書を折々に開いては、スキルアップに腐心する日々だ。
生きがい
現状では専用窓口を訪れ、就職に至った患者は、回復傾向にあって体調が良好な人に偏っている。治療中で定期的に通院が必要だったり、抗がん剤の副作用に苦しんでいたりする患者が就職できるケースは少ない。小沢さんは「『入院して家族に迷惑を掛けたので、働いて元気な姿を見せたい』という人もいる。さまざまな価値観に応じた就労環境があるのが理想」と話す。
内閣府が13年1月に実施した「がん対策に関する世論調査」の結果によれば、がんの治療や検査で2週間に1回程度通院する必要がある場合、働き続けられる環境だと思うかと聞いたところ、「そう思わない」と回答した人が68・9%を占め、「そう思う」は26・1%にとどまった。
国のがん対策について、どういったことに力を入れてほしいと思うかとの問いには、「がんの早期発見(がん検診)」(67・2%)、「がん医療に関わる医療機関の整備(拠点病院の充実など)」(54・2%)に次いで「がんによって就労が困難になった際の相談・支援体制の整備」(50・0%)が挙がった。
小沢さんが訴える。
「がん患者になっても希望や目標を持つことで生き生きとした生活を送れる。それに応えてくれる企業が必要だ」
自身は定年後に資格を取得し、ハローワークに勤めるようになった。働くことを支える仕事-。都内の私立中高一貫校で事務職に就いていたころ、生徒たちにアドバイスしたことにその原点がある。不良の子が就職という人生の岐路に向き合い、自らの存在意義を見いだし、成長していく姿に目を見張った。
小沢さんは今、より困難な状況で就職がかなったがん患者から感謝の言葉を掛けてもらうことに「やりがいを感じる」。人の役に立ち、その手応えが得られてこその人生。がんとともに生きる時代、窓口を訪れる患者は「妥協せず、志望する仕事をしたいという強い思いを抱いている人が多い」。がん宣告で見失いかけた希望をそうして取り戻そうとする姿に、働くことの意味をあらためて見る思いがしている。
NPO法人「がん患者団体支援機構」などが09年に行ったアンケートでがんと診断された後の仕事の変化を尋ねたところ、「そのまま」は56%、「ほかの仕事」に変わったのは10%、「無職になった」は29%に上った。
【神奈川新聞】
«「がん患者の就活(上)。」へ戻る。
«「がん患者の就活(中)。」へ戻る。
2015年01月07日
がん患者の就活(中)。
「がん患者の就活(上)。」より続き。
やはり、社会復帰出来ることが治療の1つの節目だと思います。私も早く復帰したい。美味しいものを存分に味わえる身体が欲しい。ボウリングに熱中したい。
«「がん患者の就活(上)。」に戻る。
»「がん患者の就活(下)。」に続く。
やはり、社会復帰出来ることが治療の1つの節目だと思います。私も早く復帰したい。美味しいものを存分に味わえる身体が欲しい。ボウリングに熱中したい。
がん患者の就活(中)「仕事を生きる目標に」励みーカナロコー
がんの病歴を企業側に申告するのか、しないのか。就職活動の際、どちらを選択するか悩む患者は少なくない。
白血病を患った横浜市在住の金田洋二郎さん(51)=仮名=は迷った末、申告して就職活動を続けている一人だ。
「がんのことを隠して就職しても、周囲の理解がなければ働き続けるのは難しい。だから私は隠さない」
もっとも、はかばかしい結果はなかなか得られず、「がん患者だからとむげに断れず、とりあえず面接はするという雰囲気を感じることもある」とこぼす。
発症は2010年5月。全身のだるさが続いたため、横浜市内の病院で検査を受けて判明した。
入院し、5カ月にわたる抗がん剤治療で快方に向かった。体力の低下を考慮して治療をやめ、自宅で療養に切り替えた。ところがほどなく再発。骨髄移植を受け、その後の経過は良好で今は治療も受けていない。
発症当時はコンピューターのメンテナンスなどを個人で請け負って生計を立てており、会社の設立も考えていた頃だった。起業の夢を諦めたわけではないが、自分の状態を考え、現実的な選択として就職を目指すことにした。
就活で病歴を伝えようと考えるようになったのは、病歴を伏せて働くことの難しさをがん患者がつづったインターネットサイトで見かけてからだ。
「不利になるのは分かっていたが、就労後のことを考えると最初に言った方がいいと思った」
切実な思いもそこに重なる。
「病気になっていない人がこちらの状況を理解することは難しい。私たちが支援の必要性を訴えていくしかない。病歴を明かしていくことには、そういう意味も込めている」
国立がん研究センターの調査では、08年にがんと診断された患者は約80万人で、うち20~64歳が約25万9千人と全体の32・4%を占める。つまりがん患者の3人に1人は働くことのできる年齢でがんにかかっている。
◇理解なく
就活で不採用の理由を知らされることはほとんどないが、体への負担を企業の方から懸念されたこともあった。
実際、抗がん剤治療や骨髄移植の影響でわずかに小走りするだけで息が上がるようになった。金田さん自身、体力の低下を感じているが、「多少の不自由はあっても1、2時間の立ち仕事なら問題はない」という。
だが、それを例えば面接の場で本人の口で説明し、企業側に理解してもらうのは容易ではないと感じる。「休みがちになり、会社に迷惑を掛けてしまうのは分かっている。特に中小企業は余裕がない会社も多いと思う。健康な人と同じ給料をもらおうだなんて考えていない。労働力に見合う形で雇ってほしいのだが」と訴える。
厚生労働省によれば、がん治療のために通院しながら働いている人は約32万5千人(男性約14万4千人、女性約18万1千人)。治療から就職まで一貫した支援制度の必要性を痛感する金田さんが言葉に力を込める。
「社会復帰してはじめて、治療が終わったと思うようにしている」
厚労省の合同研究班ががん患者に調査を行ったところ、会社勤めしている人の34%が依願退社か解雇されており、自営業者等の13%が廃業していた。そうした現状を知り、金田さんは「休職した人が復帰できる場所を残してほしい。社会的な支援が必要だが、企業側の理解が深まれば状況は変わってくるはず」と指摘する。
◇両立支援
金田さんは今、がん患者を含めた長期療養者の就労支援制度を利用している。13年5月からハローワーク横浜(同市中区)と横浜市立市民病院(同市保土ケ谷区)が連携して取り組んでいる国のモデル事業だ。
主眼に置くのは治療と就労の両立の支援。厚労省が実施したアンケートなどから、「8割の企業ががん患者雇用を柔軟に対応していない」「6割の企業に相談窓口がない」「がんに罹患(りかん)しても働けるということを患者や事業所に説明し理解を得る」「コーディネーターが治療計画と復職計画を患者や事業所と情報共有し、障壁を交通整理して仲介・調整する」といった現状と課題が浮き彫りになった。
金田さんはハローワークを訪ね、担当スタッフに病状や現在の体調、治療スケジュール、志望する職種などを伝え、条件に合った企業に申し込む。「仕事と病気のことを一緒に相談できる機会はあまりない。こちらの状況や気持ちを分かろうと時間をかけて話を聞いてくれる」とメリットを口にする。
ハローワークはそのほか、県内企業に患者支援制度を説明したチラシを配布し、企業に申し込む際には患者支援の一環であることを伝えている。就労の支援だけでなく、支援制度の存在自体の周知にも取り組んでいる。
公的な第三者の仲介によって患者の状況への企業側の理解は進むのではないか-。金田さんが期待を込めた。「仕事を生きる目標にすることができれば、病気の苦しみも前向きに乗り越えられる。生きる力になる」
【神奈川新聞】
«「がん患者の就活(上)。」に戻る。
»「がん患者の就活(下)。」に続く。
2015年01月06日
がん患者の就活(上)。
癌と闘いながらそれでも働かなくてはならない人達が、世の中にはごまんといます。
私は数年前にすい臓癌を患って手術を受け、まともに働くことが困難な身体になりましたが、経済的にはさほど困窮している訳でもなく、障がい者年金を受給出来るのならとそれで生活する道を選びました。
それを見た神様が「再び働く意志がないなら、一生病気で苦しんでいればいい。」と怒ってしまったのかもしれません。
でも遊んで暮らすつもりはありませんでした。もはやデスクワークしか出来そうになく、求人情報を見るとWord・Excelの操作が最低条件のところばかりなのでとりあえずパソコン教室に通っておこうと行動を起こしました。縁あって職業訓練の臨時講師の仕事もいただきました。
これからは収入にこだわらず時間に縛られることのないボランティアレベルでの社会貢献が出来ればそれでいいと思っていた矢先の白血病だったのです。
そんな私にとって少し耳の痛い記事を発見しました。
»「がん患者の就活(中)。」へ続く。
私は数年前にすい臓癌を患って手術を受け、まともに働くことが困難な身体になりましたが、経済的にはさほど困窮している訳でもなく、障がい者年金を受給出来るのならとそれで生活する道を選びました。
それを見た神様が「再び働く意志がないなら、一生病気で苦しんでいればいい。」と怒ってしまったのかもしれません。
でも遊んで暮らすつもりはありませんでした。もはやデスクワークしか出来そうになく、求人情報を見るとWord・Excelの操作が最低条件のところばかりなのでとりあえずパソコン教室に通っておこうと行動を起こしました。縁あって職業訓練の臨時講師の仕事もいただきました。
これからは収入にこだわらず時間に縛られることのないボランティアレベルでの社会貢献が出来ればそれでいいと思っていた矢先の白血病だったのです。
そんな私にとって少し耳の痛い記事を発見しました。
がん患者の就活(上)「正直に言いたい」葛藤続くーカナロコー
日本人の男性の2人に1人、女性の3人に1人がかかるとされるがん。医療技術の進歩で生存率が高まる一方、患者が体調や治療状況に応じて働ける場は整っていない。病気と向き合いながら、生活の糧や生きがいを求めて就職活動に励む患者は何を思うのか。現場の声を届ける。
◇
不採用という非情な通告に落胆しながら、どこか冷めた目で折り合いをつけようとする自分がいた。
「俺が雇う立場だったら、ちょくちょく休むヤツなんか採用しないだろうな、と」
そう考えていた当時を思い、西岡裕也さん(45)=仮名=の顔に自嘲の苦い笑みが浮かんだ。
勤めたばかりの物流会社から不採用の知らせを受けたのは昨春のことだった。「試用期間だったし、あの時は仕方がないと考えた。いまでは、もっとこちらの身になって考えてほしかったと思っているが」。手元に重ねられた求人票にふっと目線を落とした。
◇病歴隠し
高熱が出て入院を余儀なくされたのは、働き始めて4日目のことだった。体調不良を理由に2日間欠勤し、詳しい原因は上司に説明しなかった。
高熱の理由は、その1年ほど前に受けた胆管切除手術の影響だった。
がんだった。「でも、本当のことを言うとインパクトが強いので伏せることにした」。それでも2日後、上司は言った。「会社から連絡があって、不採用になった。申し訳ない」
がんになる前、すでに仕事を辞めていたが、術後に体調が安定してから復職を目指してきた。免許を持つフォークリフトを操り、倉庫内を行き来して自動車部品を運ぶ仕事に魅力を覚えていた。「体調のことで同僚に迷惑が掛からず、スキルが生かせる。やっと条件に合う仕事に就けたと思ったのだが」。病歴を伏せたまま働く難しさを実感した。
◇壁の存在
がん告知は2012年9月。自宅近くの藤沢・鵠沼海岸で趣味のサーフィンを楽しんでから1週間ほど全身のだるさが抜けなかった。「日焼けしたせいかな」と気にしていなかったが、糖尿病でかかっていた主治医に相談すると検査を勧められた。
胆管がんだった。幸い早期発見で、通院しながら約3カ月の抗がん剤治療を受け、13年2月にがんを切除した。
手術は成功。だが、胆管を切除した影響で40度近い発熱を繰り返した。そのたびに入院を余儀なくされた。
体調が安定したのはその年の6月ごろから。社会復帰を考えはじめた。「そろそろ働けるかな」「どのくらい動けるだろうか」。期待と体力低下の不安が交錯した。
就職活動を始め、2社で面接を受けた。がんのことは伏せた。体力面の不安や治療による欠勤など会社側に悪いイメージを与えてしまい、不利になると考えたからだ。
ブロック塀や門扉など住宅用外構資材の卸売業者に採用された。労働時間は1日約10時間、10キロ以上ある資材を運ぶこともある仕事だったが、「どれだけやれるか試したかった」。会社の経営面に不安があったために約4カ月で退職したが、「自信が持てた」。
数カ月後、自動販売機の設置業者に再就職した。同僚数人とトラックで1日約10カ所を回った。手術後は便通が1日10回に上ることもあり、移動時に何度もトラックを止めてもらった。「同僚に迷惑を掛けているのではないか」との思いがもたげ、1週間でやめることになった。
できることとできないこと、無理解と理解してもらうために必要な働き掛け、その勇気。折々で見えない壁を感じた。
◇働く意味
病気という名の壁が存在することを痛感したのはこれが初めてではなかった。
高校入学を間近に控えていた頃、箱根町の自宅で寝ていて意識を失った。明け方に病院に搬送され、検査の結果、糖尿病と判明した。1日4回のインスリン注射が欠かせなくなった。
その後はほとんど病状に悩まされることなく学校生活を送った。3年生の時、卒業後に就職することを決めた。大手鉄道会社に興味を持ち、担任教師に会社へ問い合わせてもらった。
回答は「病気があるので採用はできない」だった。
当時の西岡さんには「そんなものか」と受け止めることしかできなかった。
母親の知人を頼って相模原市の自動車部品販売会社に就職し、その後は接着剤メーカーなど数社を転々とした。病歴を明かすことはほとんどなく、やがて「病気は就職に不利」という考えが自分の中で固定化していった。
「一般的にがんイコール死というイメージが強い。長い間、働けるか分からない人を企業が雇うはずはないと考え、がんのことを正直に言おうとは思わなかった」
一方で葛藤を抱え込んでもいた。
「風邪などを理由にして休んでいたが、ちょっとしたことで仕事を休むヤツだと思われるのが悔しかった。いいかげんな気持ちで働いているわけじゃないんだと言いたかった」
本音はこうだ。
「理解してもらえるなら、正直に言いたい」
がんが「国民病」と呼ばれるようになり久しい。なのに、ひとたびかかれば人生の苦境に立たされるような社会でよいのか、という疑問がわく。思わぬがん告知によって限りある命の尊さを知り、働く意味にも思索はめぐった。
「もちろん収入を得る意味もあるが、必要とされることで自分の存在価値を実感したい」
隔絶を肌で感じるいま、仕事という社会との接点の大切さをより強く思う。
交際している女性がいる。経済的に支えられていることが心苦しいと打ち明け、西岡さんは続けた。「ちゃんと仕事に就き、彼女にも必要とされるようになりたい」
【神奈川新聞】
»「がん患者の就活(中)。」へ続く。
2014年12月30日
本日の静岡新聞にやつがれさん。
本日の静岡新聞の朝刊に「作業服屋のつぶやき 【ユニフォームのツバメヤ】」のやつがれさんを発見。
社長の気持ち、ユニホームに同封 富士の専門店が新サービス-アットエスより引用-
創業50年を超える富士市吉原商店街の作業服専門店「ツバメヤ」(竹下朋宏代表)は、会社社長がメッセージカードを添えて日ごろの感謝の気持ちを社員に伝える「社員応援ユニフォーム」の販売を開始した。
社内でのコミュニケーションツールとしての機能や社員のモチベーション向上のきっかけになればと考案。ユニホームには、受取人の社員と社長の名前に加え、社長からの無料のメッセージカードが同封される。メッセージカードは「いつもありがとう」「風邪に気を付けて頑張ってくれ!」などの20サンプルのほか、15文字以内のオリジナル文書にも対応する。
竹下社長は「メッセージなら照れくさい気持ちも伝えられる。ちょっとでも喜んでもらえたら」と話した。
社員への感謝のメッセージカードを添えたユニホーム=富士市のツバメヤ
2014年12月29日
「墓碑銘2014」。
年末の新聞に「墓碑銘2014」が続けて特集されていました。
菅原文太さんや高倉健さんは記憶に新しいところですが、宇津井健さんややしきたかじんさんも今年逝かれたばかりだったんですね。
その中で私にとって一番ショックを受けた方は、声優の永井一郎さん。次の磯野波平の声を誰がやるのかとか、しばらく話題になっていました。思い返すといつも涙が出ます。




改めて、ご冥福をお祈りします。
菅原文太さんや高倉健さんは記憶に新しいところですが、宇津井健さんややしきたかじんさんも今年逝かれたばかりだったんですね。
その中で私にとって一番ショックを受けた方は、声優の永井一郎さん。次の磯野波平の声を誰がやるのかとか、しばらく話題になっていました。思い返すといつも涙が出ます。




改めて、ご冥福をお祈りします。
2014年12月07日
今日もやってます。「いでぼく感謝祭」。
こちらは本日の岳南朝日新聞。

昨日行った際にはちょうど社長夫人が蕎麦を担当していたので、次のあんとさん祭りにはまたチラシを置かせていただくようお願いしてきました。
今日は私は出向きませんが、また昼食に焼きそば買ってきてもらおうかな。

昨日行った際にはちょうど社長夫人が蕎麦を担当していたので、次のあんとさん祭りにはまたチラシを置かせていただくようお願いしてきました。
今日は私は出向きませんが、また昼食に焼きそば買ってきてもらおうかな。
画像付き最新記事
アクセスカウンタ
ブログ内検索
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
カテゴリー
カスタマイズ (8)
└
ホームページ (4)
└
HTML (49)
└
ブログ (34)
└
画像加工 (33)
└
備忘録 (4)
スパム対策 (3)
└
Facebook(スパム) (57)
└
迷惑コメント (42)
面白画像 (173)
└
面白映像 (16)
└
面白商品 (10)
└
閲覧注意! (180)
ブロガー訪問 (3)
└
イーラ・ブロガー (39)
SNS (2)
└
Facebook(SNS) (35)
イベント (7)
└
ブログ村 (60)
└
ブロガーさん出店 (16)
└
イーラ・パーク関連 (28)
└
勉強会 (6)
└
M-netパソコンスクール (3)
ボウリング (44)
└
友の会週例会 (39)
つぶやき (186)
脳トレ (28)
雑学 (74)
ニュース (13)
└
インターネット (118)
└
TV (134)
└
新聞 (61)
リハビリ・闘病 (206)
└
膵臓癌 (11)
└
白血病 (272)
職業訓練 (1)
YouTube投稿 (1)
写真 (18)
ペット (11)
深イイ話 (25)
└
笑える話 (17)
└
怖イイ話 (8)
アフィリエイト (5)
お気に入り (3)
└
お気に入りの本(作家) (17)
└
お気に入りの音楽(アーティスト) (12)
└
お気に入りの映画・ドラマ (7)
過去記事
最近のコメント
JorgeGex / 閲覧注意!「写真でボケて」・・・
エルゼメキア / ネットでみつけた面白画像(10・・・
イルクーツクの空 / 「恐怖のズンドコ」事件。
ユーコリン / 好きなCM、嫌いなCM。(1)
ダニー / 咳に効く市販薬は?
河童工房(^◇^) / 新手のスパムアカウントに注・・・
まゆゆ♡ / ブログ免許証。
nozomi / ブログ免許証。
SemiPro(佐野進一) / 今村さんちの香りしいたけを・・・
今村さんちの香りしいたけ 店長つぐりん / 今村さんちの香りしいたけを・・・
タグクラウド
面白画像
写真でボケて
カスタマイズ
ブログ村
ボウリング
友の会週例会
ブロガー訪問
猫
迷惑コメント
リハビリ
犬
イベント
禁止ワード
雑学
IPアドレス
GIFアニメ
ドラえもん
marquee
てっぺん静岡
錯覚画像
ウルトラマン
静岡がんセンター
面白映像
駿香楼
ジェネレーター
いずのくに
静岡発そこ知り
神田商店街
介護
テレビ静岡
桃太郎
面白商品
テーブル
table
ポエム
恋の物語
ふじのみや
マンスリーチャンピオン決定戦
写真加工
秋の収穫祭 in 笑顔農園
ぎっくり腰
介護ドキュメント
マンスリーチャンピオンチャレンジ戦
ホームページ素材
WEB画像
ブログランキング
クリッカブルマップ
入院
久保ひとみ
脳トレ
QRコード

読者登録





 静岡の水産加工品を、県内各地で開かれる食や物販のイベント「マルシェ」でPRする活動を始めた。被災地と交流のある同市清水区由比の桜エビ漁師の要望がきっかけ。単に商品を販売するだけではなくレシピや食べ方も併せて紹介しながら商品価値を発信し、復興支援につなげる考えだ。
静岡の水産加工品を、県内各地で開かれる食や物販のイベント「マルシェ」でPRする活動を始めた。被災地と交流のある同市清水区由比の桜エビ漁師の要望がきっかけ。単に商品を販売するだけではなくレシピや食べ方も併せて紹介しながら商品価値を発信し、復興支援につなげる考えだ。

 県はこのほど、地域課題をビジネスの手法で解決するコミュニティービジネスの事例を集めた冊子「県コミュニティビジネス事例集2014」(A4判、60ページ)を発行した。県内でコミュニティービジネスを展開する24の会社や団体などを取り上げた。
県はこのほど、地域課題をビジネスの手法で解決するコミュニティービジネスの事例を集めた冊子「県コミュニティビジネス事例集2014」(A4判、60ページ)を発行した。県内でコミュニティービジネスを展開する24の会社や団体などを取り上げた。 着物姿で多彩な体験や人との出会いを楽しめる空間を目指した「きらく場」が25日、三島市大場の呉服・洋品店「よしだ」の一角にオープンする。企画したのは、同店の吉田智美さん(47)。「堅苦しいと思われがちな着物に親しめる場所と機会を提供したい」と意気込んでいる。
着物姿で多彩な体験や人との出会いを楽しめる空間を目指した「きらく場」が25日、三島市大場の呉服・洋品店「よしだ」の一角にオープンする。企画したのは、同店の吉田智美さん(47)。「堅苦しいと思われがちな着物に親しめる場所と機会を提供したい」と意気込んでいる。 県庁にほど近い横浜市中区のハローワーク横浜。相談窓口が仕切りを隔てて並ぶフロアの一角に専用窓口が設けられている。デスクには「長期療養者職業相談窓口」と記された手作り表札が。「あまり目立つと利用者が気にするから」。スタッフの小沢美弘さん(68)が配慮を口にした。
県庁にほど近い横浜市中区のハローワーク横浜。相談窓口が仕切りを隔てて並ぶフロアの一角に専用窓口が設けられている。デスクには「長期療養者職業相談窓口」と記された手作り表札が。「あまり目立つと利用者が気にするから」。スタッフの小沢美弘さん(68)が配慮を口にした。
 がんの病歴を企業側に申告するのか、しないのか。就職活動の際、どちらを選択するか悩む患者は少なくない。
がんの病歴を企業側に申告するのか、しないのか。就職活動の際、どちらを選択するか悩む患者は少なくない。 日本人の男性の2人に1人、女性の3人に1人がかかるとされるがん。医療技術の進歩で生存率が高まる一方、患者が体調や治療状況に応じて働ける場は整っていない。病気と向き合いながら、生活の糧や生きがいを求めて就職活動に励む患者は何を思うのか。現場の声を届ける。
日本人の男性の2人に1人、女性の3人に1人がかかるとされるがん。医療技術の進歩で生存率が高まる一方、患者が体調や治療状況に応じて働ける場は整っていない。病気と向き合いながら、生活の糧や生きがいを求めて就職活動に励む患者は何を思うのか。現場の声を届ける。